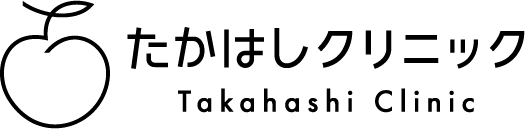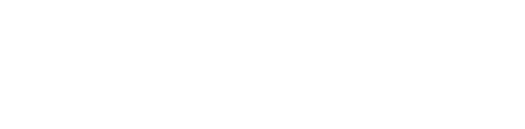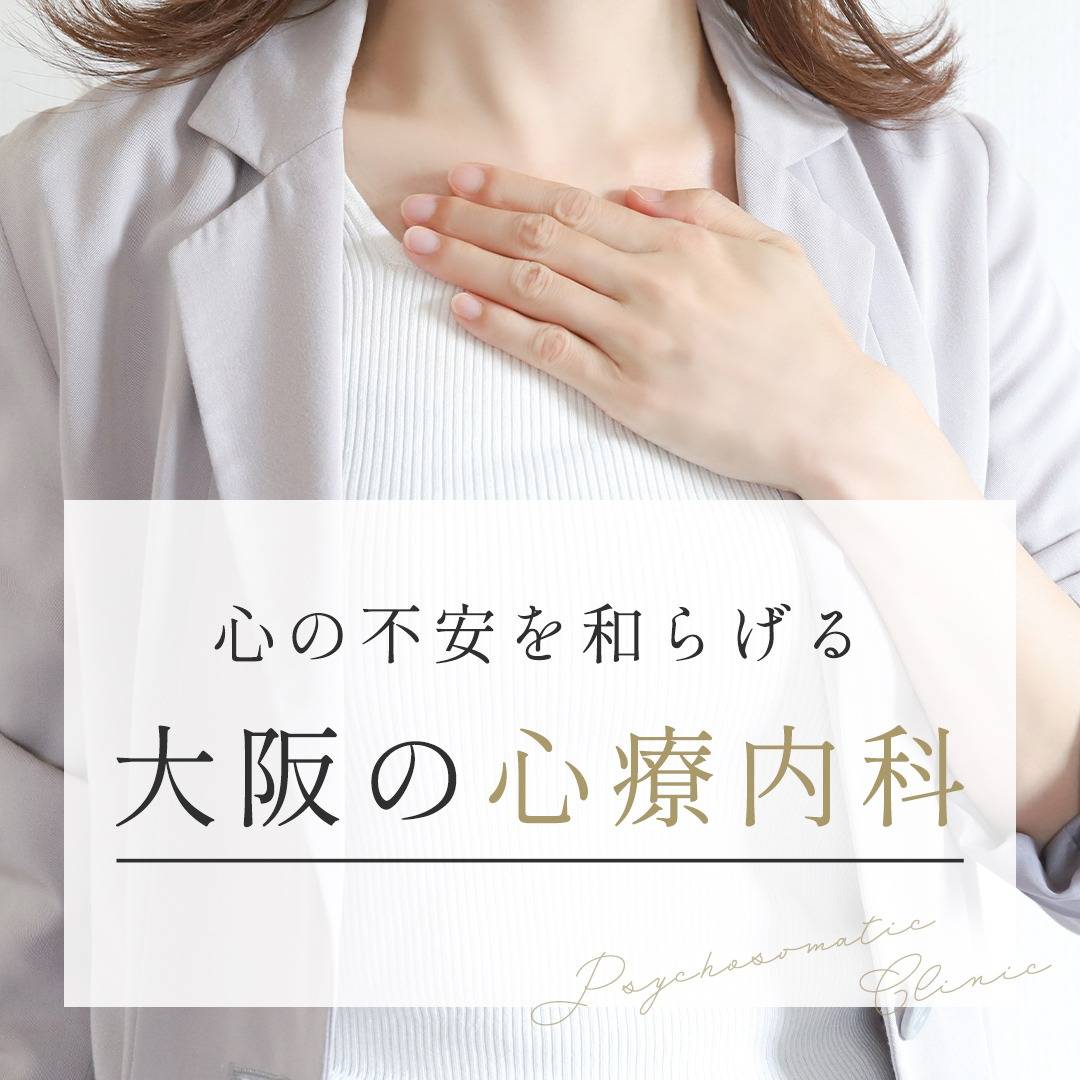双極性障害における薬物療法
2025/10/04
双極性障害は、気分の大きな波を特徴とする精神疾患であり、その治療には継続的な薬物療法が不可欠です。精神科の分野では、症状の安定化と再発予防を目指し、多様な薬剤の組み合わせや新たな治療法の研究が進められています。本ブログでは、近年の研究成果や臨床データをもとに、双極性障害における薬物治療の知見をわかりやすく解説します。患者さま一人ひとりに適した治療戦略の理解を深め、生活の質向上に役立つ情報を提供することで、より良い治療選択の一助となることを目指します。精神科での実践的な薬物療法の現状を知りたい方にとって、信頼できる情報源となることを願っています。
目次
双極性障害の治療。気分の波を安定させる。
双極性障害は、躁状態とうつ状態の間で気分が大きく変動する精神疾患で、患者の生活に多大な影響を及ぼします。症状の波は突然現れ、日常生活や人間関係に葛藤をもたらすことがあります。薬物治療は、この気分の不安定さを抑え、安定した状態を維持するために不可欠です。近年の研究では、気分安定薬の炭酸リチウムや一部の抗てんかん薬が依然として有効とされる一方で、新しい抗精神病薬の有用性も示されています。また、個々の症状や副作用のリスクに応じた薬剤の組み合わせや用量調整が重要視されています。さらに、早期からの継続的な治療介入が再発予防に効果的であることが明らかになっており、患者の生活の質向上に寄与しています。精神科では、こうした最新の知見を取り入れ、患者さんごとの最適な治療戦略を構築しています。双極性障害の薬物治療を通じて、より安定した日常を目指すための理解を深めましょう。
薬物治療の基本:気分安定薬
双極性障害における薬物治療は、主に気分安定薬を用いて行われます。狭義の気分安定薬は炭酸リチウムと一部の抗てんかん薬を指します(ラモトリギン、バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン)。加えて最近は第2世代抗精神病薬(クエチアピン徐放剤、ルラシドン、オランザピン)も双極性障害の治療に有効とわかり広義の気分安定薬とされます。これらの多くは躁状態と鬱状態の両方に効果があり維持期も継続して内服が必要となってきます。また多くの患者さんでは気分安定薬、抗精神病薬どちらか単剤での改善・維持は困難であり併用して治療されることがガイドラインでも推奨されています。
躁病相の治療
躁状態は患者さんの経済的・名誉的社会的損失が大きく一刻も早く上がりきったテンションを下げねばなりません。前述の気分安定薬および抗精神病薬を多めの量投与し鎮静をかけます(炭酸リチウム・バルプロ酸ナトリウムでは1200~1600mg、抗精神病薬では最大量。軽躁ではもう少し少なめ)。前ブログで記載したⅠ型双極性障害の躁状態では病識がなく内服すら困難な場合も多いため隔離室を必要とすることも稀ではありません。また、外来治療では過鎮静や他の副作用に注意して慎重に処方量を判断しなければなりません。薬物療法を継続できれば多少時間を要しても躁は落ち着いていきます。
うつ病相の治療
うつ病相の治療では炭酸リチウム、ラモトリギン、クエチアピン、ルラシドン、オランザピンが有効とされています。双極性障害うつ病相の厄介なところはこれらの気分安定薬を用いてもなかなか気分が上がってこないということです。うつなんだから抗うつ薬を使えば良いのでは?と思われるかもしれませんがそう単純な話でもありません。双極性障害のうつに抗うつ薬を用いると躁転や急速交代型(ラピッドサイクラー)化などにより不安定化してしまいます。ですので以前は抗うつ薬は用いないというのがコンセンサスでした。しかしながら実際の治療では気分安定薬のみで粘っていると年単位でうつが遷延することも普通にあり得ます。これでは患者さんの損失が大きすぎますので近年は、必ず気分安定薬を併用のもと、という前提でSSRIなどの抗うつ薬の使用が認められていますし、実臨床的に妥当な対応だと思います。維持期も気分安定薬のみが理想ですが少量の抗うつ薬がある方が安定される方もおられます。また薬物療法に反応しない場合や自殺の危険が切迫している例では電気けいれん療法(ECT)も適応となります。
双極性障害の治療の実際
双極性障害の薬物治療は、症状の安定化と再発予防を目的として長期的な管理が求められます。躁やうつを改善しそれらが再発しないように維持する。しかしながら実生活でのさまざまなストレスやライフイベント、怠薬等などにより再燃再発は少なくなく凪の状態を維持するのは簡単ではないのが実情です。精神疾患のなかでも双極性障害の治療はかなり難しいものと考えている治療者が多いのではないのでしょうか。
まとめ
双極性障害の薬物治療は、症状の安定化と再発予防が最も重要な目標です。炭酸リチウムやラモトリギンなどの気分安定薬が依然として有効性の高い治療選択肢であることが確認されていますが、副作用管理の工夫も欠かせません。さらに抗精神病薬も症状のコントロールに用いられ、併用療法によって患者一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせた個別治療が推奨されています。また、新しい薬剤の開発やエビデンスに基づく治療ガイドラインの更新により、より安全で効果的な治療法の提供が進んでいます。精神科の現場では、日々患者さんの安定した精神状態を維持できるよう工夫と研鑽を重ねています。
----------------------------------------------------------------------
たかはしクリニック
住所 :
大阪府大阪市生野区巽南5丁目7−26 2F
電話番号 :
06-6794-0333
大阪での不調をケアする精神科・心療内科
休職を考える方を大阪にある当院で支援
----------------------------------------------------------------------